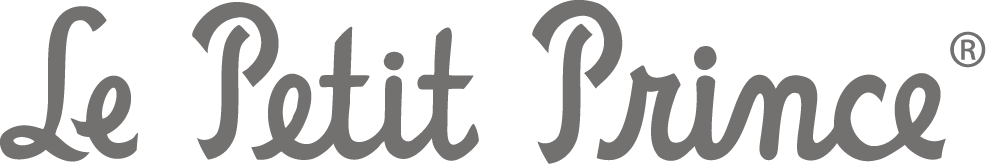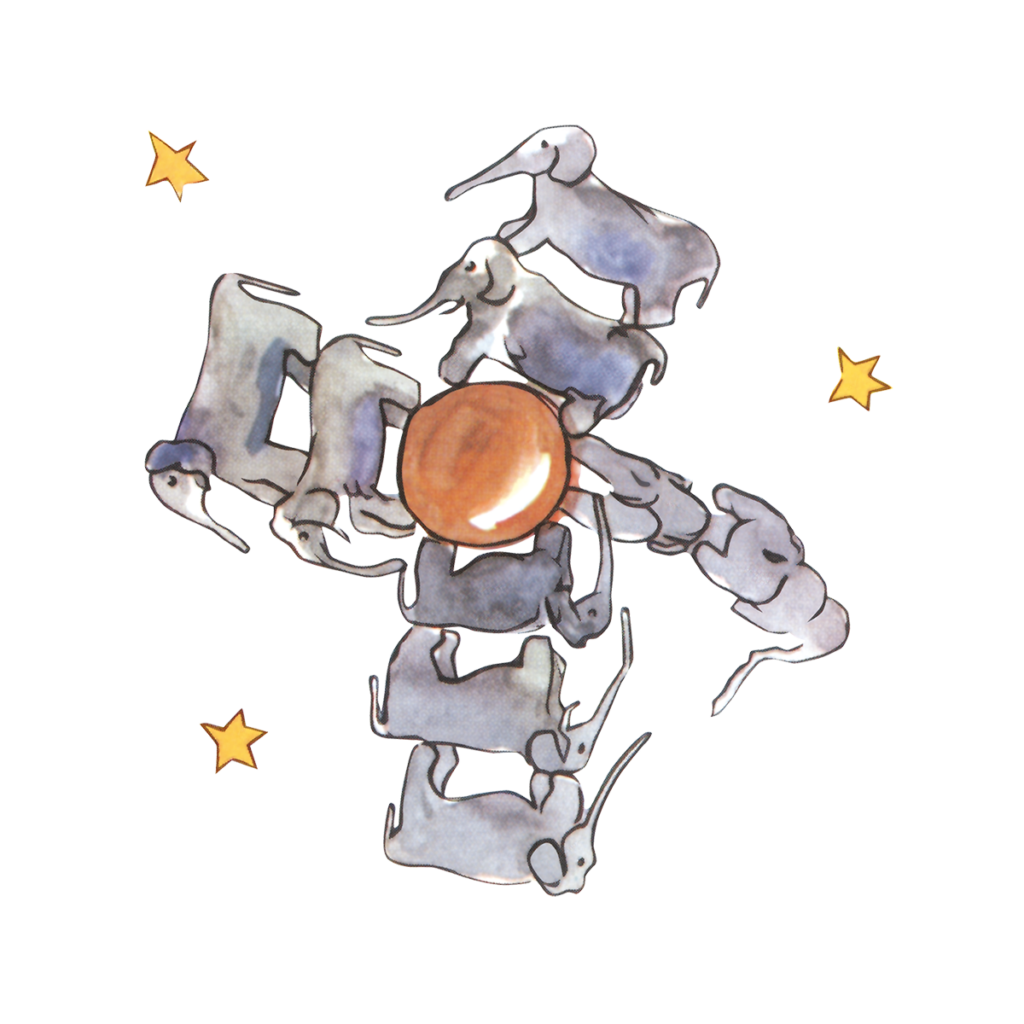星の王子さまとは
概要
『星の王子さま』は、フランスの世界的ベストセラー作家、アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの遺作にして代表作です。語り手の飛行士が、飛行機の故障で不時着したサハラ砂漠で不思議な男の子=星から来た小さな王子さまと出会い、絆を結び、別れるまでの十日間と、その間に飛行士が聞き知った王子さまの旅路とを描いています。登場人物を通して語られる「l’essentiel(レソンシエル)=本当に大切なもの」についての著者のメッセージは、地域・言語・文化、性別や年齢、そして時間の壁を越え、今も読む者に感動を与え続けています。
サン=テグジュペリ自身、フランス航空史に名を遺す飛行士でもありました。作家としても、当時人類にとって新しい体験だった「飛行」を初めてまざまざと言語化し、またその体験から得た人間性についての洞察を文学に昇華した作風で知られています。本作執筆の六年前には実際に砂漠に不時着し、四日間さまよったあと奇跡的に隊商に発見され生還するという経験をしています。
第二次大戦中の1943年に出版されて以来、今日まで八十年間に五百を超える国と地域の言葉に翻訳され(聖書に次ぐ数と言われています)、累計発行部数は二億冊に及び、現在も年に二百万部以上が発行されています。人類史上最も多く読まれている本の一つと言って過言ではありません。
日本では1953年に岩波書店から内藤濯氏による翻訳が出版されました。2005年に日本での著作権保護期間が終了すると、多くの出版社から新訳による出版が相次ぎ、翻訳の数は今日までに三十以上、本の種類では五十以上にもなります。電子書籍のダウンロード数を含めた累計発行部数は一千万部を超えています(注)。
『星の王子さま』の原題(フランス語)は”Le Petit Prince”。逐語訳すれば「あの小さな王子」となりますが、最初の出版から五十年以上にわたり唯一の翻訳だった内藤訳の、周知され定着しているタイトルを、多くの新訳も(当公式サイトも)踏襲しています。その理由は知名度だけではありません。Petitが持つ単に小さいという以上の親愛のニュアンスをひらがなに開いた「さま」に託し、日本語ではあまり顧みられない定冠詞Leの特定する役割を、「こういう時に日本では古来、その人が住むところの名を冠した」(池澤夏樹「タイトルについての付記」・集英社「星の王子さま」)ことを踏まえて「星の」と訳出したこのタイトルが、まさに名訳であることが最大の理由でしょう。
注:2017年公表の岩波書店の累計発行部数=660万部と、2022年公表のゴマブックスの累計ダウンロード数=350万DLの合計。他の出版社は含まず。)
https://www.iwanami.co.jp/files/eigyou/POP/prince.pdf
http://www.goma-books.com/archives/63374
物語
『星の王子さま』では、語り手である飛行士によって、彼自身の物語と、彼が聞き知った王子さまの物語の二つが、交差しながら語られます。
飛行士は子どものころ、ぞくぞくするような恐ろしい光景(大蛇が象を丸呑みにして消化しているところ)を描いた絵を帽子の絵だと片付けられて以来、「おとな」と彼らの関心事に違和感を持ちながら生きてきました。それは成長し大人に交じって生活するようになってからも変わらず、心からの友を得ることもできず孤独に暮らしています。社会生活を送る上では自分の中の「こども」に蓋をせざるを得ず、いつしかそれを少しずつ失いつつもありました。
そんな彼はあるとき、エンジンの故障で不時着した砂漠で不思議な男の子=星から来た王子さまに出会います。王子さまは飛行士が書いて見せた大蛇の絵に何が書いてあるのかを、当たり前のように言い当てます。飲み水が尽きるまでの一週間で飛行機を修理できなければ死が待っている状況の中、飛行士は王子さまと会話を重ね、その旅路を知っていきます。
小さな星で、たった一人寂しく暮らしていた王子さまは、ある時どこからかやってきた種から芽吹いた美しいバラの花と出会いました。王子さまはバラの美しさに感激し、かいがいしく世話をしますが、気位が高く気まぐれなバラとの会話に戸惑い傷つき、ついには離別を決意して星を発ちます。
小惑星をめぐって「とってもへん」な大人たちに出会った王子さまは、最後に地球に降り立ちます。たどり着いた庭園に咲く五千本ものバラを見て、世界に一つだけと思っていた自分の花がありふれたものだったことを知った王子さまは、花が無価値だと考え涙を流します。しかしまさにその時現れたキツネから、他者との絆について、そして絆を結んだものへの責任について学び、ある決意を胸に砂漠に戻ってきたのです。
飛行士は王子さまとの会話によって、少しずつ「本当に大切なもの」を思い出していきます。とうとう飲み水が尽き、砂漠に井戸を探して王子さまと歩く中で、飛行士はついに「こども」の自分を取り戻し、奇跡のように現れた井戸の水によって二人は絆で結ばれます。しかし、キツネの教えによってバラとの絆と自らの責任を自覚した王子さまは、飛行士に別れを告げ、バラを守るため命を顧みず星へと帰っていくのでした。
なんとか飛行機の修理を終えて生還した飛行士は、6年が過ぎた今も王子さまの帰りを待ち続けています。
執筆の背景
『星の王子さま』が初めて出版されたのは、著者の母国フランスではなく、アメリカのニューヨークでした。これには第二次世界大戦が大きく関わっています。
1939年9月、ナチス・ドイツに対してフランスとイギリスが宣戦布告すると、予備役だったサン=テグジュペリは動員され、偵察部隊で操縦士として任務につきました。しかし1940年6月にフランスはあえなくドイツに降伏。開戦前にナチを取材した経験からその非人間性を体感していたサン=テグジュペリは、アメリカの参戦が祖国を救う唯一の手段であると考え、ニューヨークへと渡ります。
しかしそこには、祖国が危機にある中、いたずらに党派に分かれ争っている亡命フランス人コミュニティの姿がありました。全フランス人の団結を訴え、いずれの党派にも与しなかった彼は、そのすべてから批判されることになります。1942年に発表した『戦う操縦士』が多くのアメリカ人に感銘を与え、「ヒトラーの『我が闘争』に対するデモクラシー側からの最良の回答」(アトランティック誌1942年4月号)と評されても、同胞からの誹謗中傷は止みません。傷つき孤独を深める彼に、出版社の知人たちが勧めたのが児童書の執筆でした。
サン=テグジュペリは1942年5月に『星の王子さま』の執筆に着手しますが、同年11月に連合軍が北アフリカに上陸すると、戦線復帰のために奔走を始めます。『星の王子さま』は翌43年4月、レイナル・ヒッチコック社から刊行されますが、サン=テグジュペリはその一週間後、祖国を救う戦いに再び身を投じるためアルジェリアへと旅立ちました。
すでに43歳で、偵察用最新鋭機の操縦の制限年齢を大幅に超えていましたが、必死の訴えにより厳しい訓練に耐え、例外的に操縦資格を得て再編された原隊に復帰します。そして翌1944年の7月31日、コルシカ島の基地から最後の任務に出撃したサン=テグジュペリは、そのまま消息を絶ちました。連合軍によるパリ解放のわずか四週間前のことでした。
本当に大切なもの=l’essentiel
心でなきゃ、ちゃんと見ることはできない。本当に大切なものは、目に見えない。(第二十一章)
『星の王子さま』は軽やかな語り口と洗練されたユーモア、子ども心をとらえる数々の不思議、そしてかわいらしい挿絵に彩られています。それらも大きな魅力ではありますが、この作品がこれほど長く、そして広く愛されているのは、そこに込められた「l’essentiel=本当に大切なもの」についての著者のメッセージが普遍的な価値を持つからに他ならないでしょう。
「本当に大切なもの」を描き出すのに、著者はまずそれを見失い、別の何かに心を捉われてしまった人々=「おとな」の愚かしさを、ユーモアたっぷりに、しかし痛烈に描きます。別の何かとは、数字、体面、他者からの称賛、逃避、所有、指示に従うだけの仕事、体験を伴わない知識などです。戯画化された「おとな」たちの姿に私たちは思わず笑ってしまいますが、その後にふと気が付くのです。自分はこうしたものに価値を置いていないのだろうか、いや、むしろこれらこそ自分が普段の生活で気にかけていることそのものではないか、と。
著者はこうしたものにすっかり捉われている「おとな」には容赦がありませんが、一方で「本当に大切なもの」を見失うことは誰にでもあることも示しています。自分の中の「こども」に蓋をして暮らすうちそれを失いつつあった飛行士は、飛行機の修理の成否が生死を分かつ状況を前に、探し求めてきた心からの友たりうる王子さまが語る言葉に真剣に向き合うことができません。その王子さまですら、世界に一つだけと思っていた自分の花がありふれたものであることを知った時、花が無価値だと考えて泣きさえしたのです。
では「ほんとうに大切なもの」を見失ってしまったとき、人はどうやってそれを取り戻すことができるのでしょう。そもそも、目に見えない「本当に大切なもの」とは何なのでしょう。著者は他の作品、『人間の土地』や『戦う操縦士』では繰り返し訴えているその答えを、この作品ではあえて、語り手の言葉として明言することはしていません。ですが代わりに、その手がかりとなる言葉をたくさんちりばめています。そこには、読む人がそれぞれ、その人なりの「本当に大切なこと」を見出せるようにという願いが込められているようです。こうした言葉こそが、『星の王子さま』の最大の魅力なのではないでしょうか。
人間はもう、何かを知るために時間を使ったりしない。なんでも出来合いのものを店で買ってくる。でも友だちは店には売ってない。だから人間はもう友だちが持てないんだ。(第二十一章)
あんたのバラをかけがえのないものにしたのは、あんたがバラのために費やした時間なんだ。(第二十一章)
誰かが何百万の星のどれか一つに咲く、たった一輪の花を愛してさえいれば、その人は星空を見上げて幸せになれる。(第七章)
おいらはパンを食べない。麦なんて用なしだ。麦畑を見たってなんとも思わない。さびしいもんさ! でもあんたの髪は金色だ。だからあんたがおいらを飼いならしてくれたら、素晴らしいことになる! 金色の麦畑を見るたび、おいらはあんたを思い出す。麦畑を吹く風の音まで大好きになる…(第二十一章)
その水は、ただかわきを満たすだけのものじゃなかった。二人で星空の下を歩き、滑車が歌うのを聞き、ぼくがこの腕で引きあげた水だ。それはまさに、心にもいい水だった。プレゼントみたいに。そうだ、小さい頃、ぼくがもらったクリスマスプレゼントがあんなにキラキラと輝いていたのは、クリスマスツリーの灯りや、真夜中のミサの音楽や、みんなの温かい笑顔があったからこそだったんだ。(第二十五章)
象徴性・寓意性
この作品を通じて繰り返し語られることの一つに、目に見えているのはものの表層に過ぎず、本質は隠されているということがあります。それを念頭に置いて読む読者は、この本は一見子ども向けのお話に見えるが本当はそうではないのかもしれず、登場する事物、人物も見える通りの存在ではないのかもしれないと考えざるを得ません。
本作が出版されて以来今日まで、大蛇ボア、象、バオバブ、バラ、小惑星の「おとな」たち、ヘビ、キツネ、井戸・・・それぞれを何かの暗喩と考える解釈が星の数ほど生まれてきました。前述した執筆の背景と、サン=テグジュペリが「行動派」の作家と呼ばれ、常に自らの体験をもとに作品を書いてきたこととを考え合わせれば、これらをことごとく戦争に関することの暗喩(例えば放置したために星を埋め尽くしてしまう三本のバオバブの樹は、枢軸三国を表しているなど)とする解釈があることも、無理なこととは言えないでしょう。
しかし著者は、明らかに象徴的・寓意的なものであっても、あくまでバオバブはバオバブとして、ヘビはヘビとして表層のみを描いています。それによって読者は、人それぞれに、あるいは読む時々で、自由で多様な読み方をすることができるのです。そのことも『星の王子さま』が愛され続ける理由の一つと言えるでしょう。
王子さまとサン=テグジュペリ
登場する人物・事物を暗喩と見る解釈で最も一般的なのが、王子さまが幼少期のサン=テグジュペリ自身(あるいは語り手の飛行士自身)とする見方です。実際、子ども時代の著者は金髪でしたし、答えを得るまで決してあきらめない性質は、そのころから変わらない彼の特徴の一つと言われています。
王子さまとサン=テグジュペリの類似性はそれにとどまりません。著者は本作を亡命先のアメリカで書きましたが、執筆後、祖国とそこに暮らす大切な人々への責任を果たすため、命がけの偵察飛行任務に復帰しました。まるで愛するものを残して故郷を離れるが、旅先で自らの責任を自覚し、それを果たすために命を賭して帰還した王子さまの行動を自らなぞるように。
さらに、不思議な符号があります。王子さまは星へと帰るのに、毒ヘビに自分をかませるという方法をとりました。体が重すぎて持っていけないというのがその理由です。しかしその翌朝、王子さまの体はどこにも見当たりませんでした。サン=テグジュペリは1944年に偵察任務中に消息を絶ち、その行方は長らく不明のままでした。50余年後の1998年、トロール船の網の中から彼の認識票ブレスレットが発見され、これをきっかけにマルセイユ沖の捜索が始まります。2年後、ついに海中で彼の乗機と思われる残骸が発見され、2003年に引き揚げられて彼の乗機と特定されました。しかし彼の遺体は、今もって発見されていないのです。